学芸員講座から得られたグスクへの興味 ―グスクの性格は変わるのか―
最終更新日:2025.07.22
はじめに
令和7年7月12日に博物館学芸員講座『第一尚氏王統期のグスク』と題して90分近くお話をさせていただきました(写真1)。昨年度もグスクの石積みについてお話をさせていただいたのですが、今回は大きく視点を変えてグスクの縄張りを中心に解説させていただきました。
写真1 学芸員講座での発表の様子
今年の7月学芸員講座は沖縄県立博物館友の会が後援であったことからか、会場である博物館講堂には160名もの方々が集まりました(写真2)。猛暑の中にもかかわらず会場へ足を運んでいただいた皆様、そして多くの参加者に対応していただきましたスタッフの皆様にはこの場を借りて感謝申し上げます。
今回はこの講座で会場から賜りましたご質問を紹介しながら、グスクの性格について取り上げていきたいと思います。

写真2 学芸員講座時の会場内の様子
1.驚きの質問内容
今回の学芸員講座では3名の方からご質問を賜りましたが、何れもレベルの高い質問であったことから最後まで緊張の糸が切れることはありませんでした。質問内容から90分間という長丁場の話を最後まで真剣に耳を傾けてくれていたことが容易に解ったことと、毎度のことではありますが、それに感謝しつつ分かる範囲で応えさせていただきました。中でもグスクの縄張りが大きく変遷していく過程で、グスクそのものの役割や性格が変わったのではないかというご質問がありましたので、ここではその点について記したいと思います。本講座ではグスクの縄張りが石積みを囲わないタイプから石積みを1重に囲うタイプ、そして石積み囲いが複数に連なるタイプへ、最終的には核となる石積み囲いが重視されてそれ以外の石積み囲いの形が規制されるタイプへと形が変化していくことをお話しました。ここではあくまで防御上の縄張りの特徴を押さえるための変遷について解説していったことから、とくにグスクそのものの機能については触れておりませんでした。
2.時間の推移で形が変化するグスク
最初に石積みがグスクに配置された段階ではその規模は小さく、石積みも野面積みに限られます(写真3)。また、内部が平坦に造成されていないグスクも見られることから恐らく、居住機能は希薄であったものと考えることができます。しかし、石積みで囲いこむ縄張りが見られるようになると、内部は平場に造成されているグスクが多く見られるようになります(写真4)。
写真3 垣ノ花グスクに見られる野面積みの石積み

写真4 船越グスク内の平場
また、遺物も一定量出土することから居住性が強くなってくるものと考えられます。この段階になると按司と呼ばれる地域の領主がグスクを拠点としていることが窺われます。そして複数の石積み囲いを連ねてくることから、グスク内部の機能が分化してくるものと思われます。それと共に一部のグスクにおいて礎石・基壇建物(写真5)とその前面に広場が見られるようになります。儀礼空間としての機能が重要視されてきたことが窺えます。加えて切石を多用した石積みが見られることからより高い石積みが求められたことが解ります。

写真5 勝連グスクの礎石・基壇建物跡と前面の広場
そして、最後に核となる石積み囲いに付随する石積み囲いが見られるグスクではまず、防御性が強く現れ出ていることと、この形のグスクはほぼ全て礎石・基壇建物とその前面に広場が見られるようになります。核となる石積み囲いを頂点に構造的な縄張りとなっていることから、儀礼を執り行う人物を中心とした権力構造がグスクに現れ出ていると見られます。この段階においては地域を統括していくための施設を抱え込んだグスクへと機能が変化していることが窺えます。琉球王国に深く関係するグスクは中心となる石積み囲いを頂点にした構造的な縄張りとなっています。
3.どの時期のグスクかによってその性格は変わる
おおよそ4つの段階にグスクはその形が変化し、それに伴って機能も変化していくことになりますが、ここでは変化していく方向性が如何様であったのかが重要になってきます。縄張りから見るとまず初めに低い石積みによる遮蔽から石積みを高層化することによって遮蔽だけでなく上部から攻撃を加えることができるといったような機能が加わっていきます。そして最終的に通路空間としての石積み囲いが出てくることにといったように防御空間の占める割合がグスク内部において広く占められるようになります。同時に居住性が強く現れるようになり、更に儀礼空間も加わり、その周辺施設が付け加えられていきます。このことは地域を統括するための政治的な施設が充実されていくことを意味します。
以上のようにグスクは大規模化されていくこととなり、最終的には琉球王国の王城である首里城のように面積が7万㎡を越えるグスクへと変化していくことになります(写真6)。

写真6 龍潭から望む首里城(塩屋尚子氏撮影)
と言うことで一概にグスクと言っても最初に石積みが配置されたグスクと首里城に見られるような大規模なグスクでは全くその性格が異なっていることは言うまでもありません。どの時期のグスクがどのような形であるのかを判断して初めて個別にグスクの性格について検証することができると言えます。
4.それでも難しいグスクの性格判断
更にグスクは15世紀後半から16世紀前半にかけて機能が大きく変化しました。どのように変化したかと言えば、グスクを拠点にしていた按司が首里へ集められ、グスクには人が住まなくなったことです。そして、グスクには聖域としての機能だけが残されることになります(写真7)。以降においては聖域がその地域の人々の手によって維持、管理されていくことになります。どこまでがグスクの聖域として古くなる部分になるのか。このことはグスクに対する人の意識の問題となるため、発掘調査で明らかにするのは困難であると思われます。

写真7 知念グスク内に見られる拝所
よって聖域としての性格が居住性や防御性より上回っていたのか否かについては現在のところ判断する術はありません。ただし、グスクの歴史においては聖域としての性格が強く現れ出ていた時期が最も長かったことだけは言えます。
このように学芸員講座で頂いたご質問は様々なことを考えていくきっかけになっていくことから、今後もこのような機会がありましたら多くのご質問を投げていただければと思います。
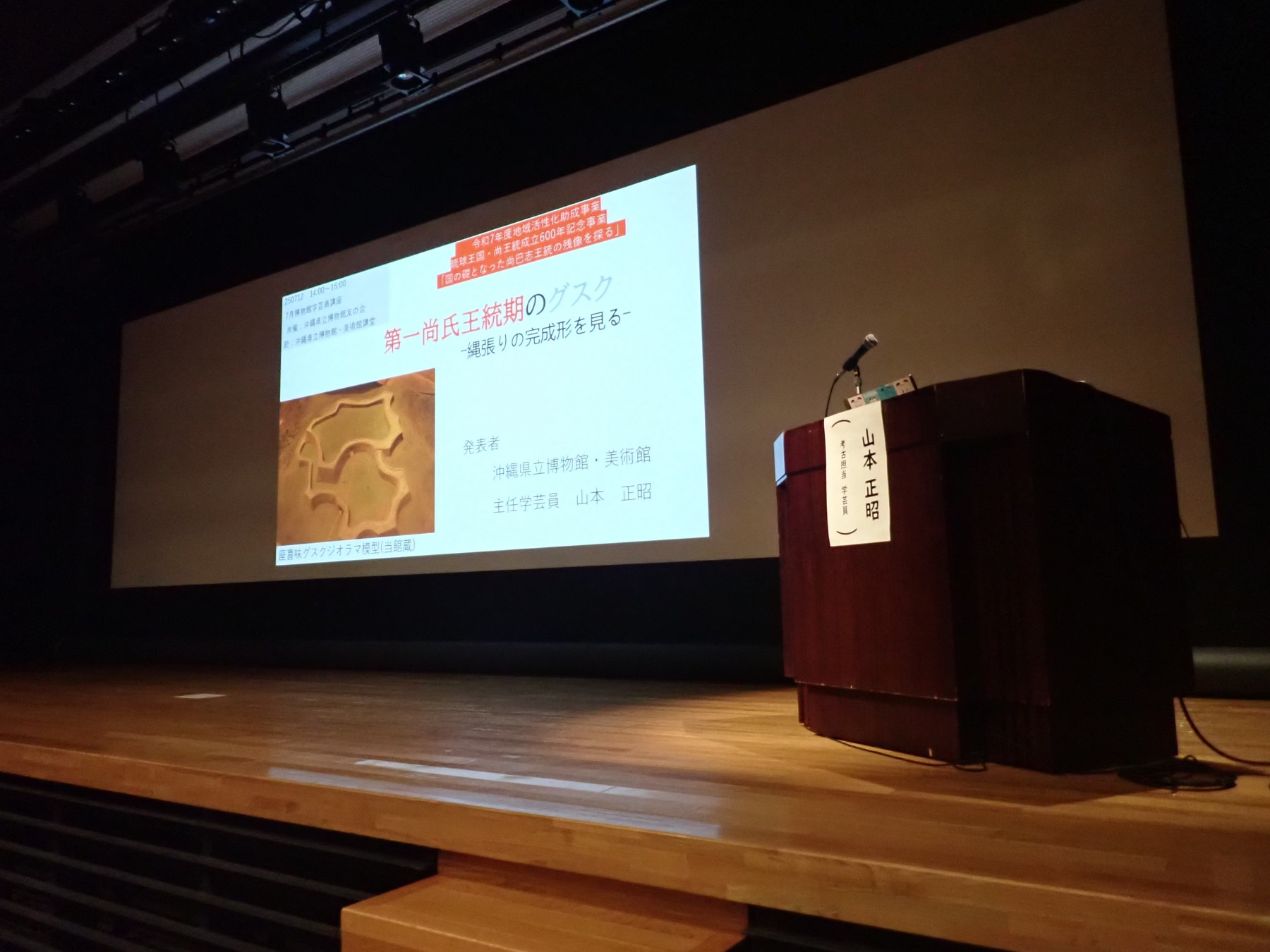
写真8 開始直前の学芸員講座の様子
最後に
ここで紹介いたしました7月学芸員講座『第一尚氏王統期のグスク』の動画が「おきみゅーちゃんねる」にて近日公開される予定です。今回の講座を聞き逃した方、また復習したい方はご覧いただければ幸いです。(沖縄県立博物館・美術館主任学芸員 山本正昭)
◆9月学芸員講座情報
9月13日(土)14時から沖縄県立博物館・美術館主催、沖縄県立博物館友の会共催で9月博物館学芸員講座「王権の痕跡―第一尚氏ゆかりの史跡を辿る―」を行います。詳しくは下のチラシをご覧いただければと思います。
博物館班 山本正昭



